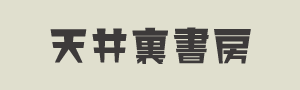志村正彦を愛した皆様へ
TAG :
WRITER
くいしん twitter.com/Quishin
あれから5年が経った。記憶を整理するのに5年という月日はきりがよくてちょうどいい。
僕にとってもそれは、悲しみを、悲しみとして告白できるくらいにしてくれる時間であった。
正直に言うと毎年この季節になると、志村について文章を書きたいと思っていた。けれど、それはできなかった。今年はなんとなくできそうだと思ったら、もう5年も経っていたという感じだ。
宇多田ヒカルが“COLORS”で歌ったように、死者に祈る際は黒い衣服に身を纏うことが一般的だ。しかし今はクリスマス。
僕らは赤い服のサンタクロースを見るたびに、ある人の死を思い出す。
赤い服を着た何者かが、大切な人を連れていってしまう悪魔ではないのかと疑ってしまう。クリスマスにそんな、世の常識から外れた異物感のあるイメージが植え付けられたのが、今からちょうど5年前。
志村正彦が、クリスマスイヴに死んだ。
今でもその日のことを鮮明に覚えている。仕事場のデスクで、訃報を知った。同時に、失うわけのないものを突然失う悲しさを知った。
Twitterに訃報が流れ始め、事実を確認するためにバンドの公式サイトをのぞいたものの、サーバがパンクしていて何も見られない。
当時、音楽雑誌出版社で働いていた。会社にはレコード会社から、志村正彦が死んだという事実を伝えるFAXが送られてきた。どう考えてもそれはウソではなかった。
正直に言って僕はまだ志村の死を受け入れていない。
また、この人ほど、「まだどこかで生きているような気がする」と言われている人を見たことがない。
2009年は変わった年だった。5月に忌野清志郎が死んだ。6月にマイケル・ジャクソンが死んだ。7月にミッシェルガンエレファントのアベフトシが死んだ。8月にレス・ポールが死んだ。多くの音楽ファンにとって、2009年は特別な年だ。
それでも、志村だけが今もどこかで生きているような気がするのは、なぜだろうか。
「若かったから」という理由もあるが、それだけではない。もしかしたらそれは志村の書いた詞のせいかもしれない。
志村の詞には時代がない。しいて言えば「日本に野球がある時代」というくらいだ。そこには携帯電話もなければ、テレビもない。時代をゆらゆらと漂うように生きたミュージシャンだった。
音楽の話のしよう。
志村正彦は、2000年以降の日本の音楽シーンにおいて、くるりの岸田繁と並ぶ天才だった。
「過小評価」という意味では、くるりの比ではないくらい、世の中にその才能がきちんと伝わっていない。それは何故か。「批評の対象にするのが難しい」からだ。つまり、その魅力を「人と話しづらい」ということである。こうして言語化しようとするのも嫌になる。
たとえば“若者のすべて”や“茜色の夕日”をピックアップして「歌詞がいいよね」と語ることはできても、“銀河”や“Surfer King”、“TAIFU”を演奏するバンドに対して「フジファブリックって歌詞がいいよね」というのは難しい。
自身のあらゆる音楽への幅広い造詣の深さと、それを咀嚼する能力が高すぎたことにより、フジファブリックの音楽は圧倒的なオリジナリティを持ってしまった。ゆえに、世の中にその魅力のほんの一部しか伝わらないままに、志村は死んでしまった。
エッセンス程度でしかないユニコーンと奥田民生からの音楽的な影響で語られるたびに、残念な気持ちになる。
岸田繁が「ブラジル音楽の話で盛り上がって、志村とは仲良くなれた」と語るくらいだ。
「その雑多な音楽性はユニコーンからの影響で〜」なんてことを言う人がいたら、それはその程度の人間だということなので、無視しよう。志村が奥田民生から受けた影響はむしろ精神性のほうが大きいだろう。この辺りは、適当に奥田民生と志村のインタビューを読み比べて欲しい。
では、フジファブリックとはなんだったのか?
「ジャンルに収まらなかった」というのはフジファブリックのひとつの魅力をわかりやすく言葉にしたものかもしれない。アジカンのパワーポップの解釈や、テレフォンズのディスコの解釈のように、鳴らしたい音、目指すべきところを限定したほうが伝わりやすい。だが、フジファブリックはそれをしなかった。これもまたくるりと同様だ。
志村が死んでからもう5年。
クリスマスイヴも終わってしまった。
結局いまだにフジファブリックとは「なんだったのか」自分にとっての答えは出ていない。志村正彦は何を伝えたかったのか、いつもこの季節になると考えてしまう。それは、一生の仕事として続いていくのかもしれない。ただ僕は志村正彦は「語られるべきだ」と考えていて、このエントリがそのきっかけになれれば嬉しい。
こんがらがった若者たちは、こんがらがった頭のままで今日も明日も生きていく。
人によっては、どこかで死んでしまう。
今年も志村の命日が終わった。
また新しい一年が始まる。
text by Quishin
![QUISHINCOM[クイシンコム]](/assets/img/logo.svg)